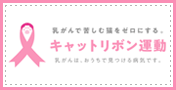日本小動物がんセンター
ホーム > 診療科目 > 日本小動物がんセンター > がんセンターの治療オプションについて
根治的治療(積極的治療)
根治的治療とは、全ての腫瘍細胞を体内から駆逐することを目的としています。
拡大外科切除
拡大外科治療とは、十分な外科マージン(正常組織と腫瘍組織の余白)を含めて腫瘍を摘出する治療です。手術手法、手術リスク、周術期合併症や入院期間等に関しては、実際に手術を担当する獣医師あるいは担当医から、その詳細が説明されます。また、各腫瘍の状態や性質によって、外科手術の前後に補助治療(放射線治療、薬物療法およびそれらの組み合わせ)が実施される場合があります。
根治的放射線治療(多分割照射)
月曜日から金曜日まで1日1回、合計18〜20回、総線量50〜60Gyが照射されます。放射線治療による副作用には下記のものが含まれます。
- ・急性障害
- 急性放射線副作用は、治療中から治療開始後約2週間程度まで徐々に照射部位の皮膚や粘膜が発赤(赤みが増すこと)、あるいは乾燥が認められるようになります。その数日後には局所的なびらんや潰瘍に発展することもあり(火傷様の徴候)、全ての放射線治療完了直後から治療完了後7日目ぐらいまでに、最大の副作用を迎えることになります。その後は約2〜4週間程度かけて正常な状態へと治っていきます。また、被毛部の局所の脱毛や皮膚の色素沈着(黒っぽくなること)も頻繁に見られます。その他、眼球が放射線照射野に含まれる場合は、白内障や網膜症によって、徐々に視力低下が認められる可能性があります。副作用の影響で十分量の食事がとれない場合、一過性の栄養サポート(食道ろうチューブや胃ろうチューブなど)が適応となることがあります。
- ・晩発障害
-
当センターの放射線治療器および治療プロトコールでは、極めてまれな副作用です。放射線照射部位に新たな癌が数年後に発生したり(二次性癌)、照射部位の骨や神経が融解(骨壊死、神経壊死)したりすることがあります。
- ・麻酔のリスク
- 主要臓器の機能がしっかりしている動物では、通常、複数回の麻酔を問題なくこなすことが可能です。
根治的放射線治療(少分割照射)
悪性黒色腫は少分割放射線治療に比較的奏効することがわかっています。少分割放射線治療では、週1回、1日1回、合計4〜6回照射されます。
定位放射線治療(SRT)
高精度放射線治療システムを用いて腫瘍部位に線量を集中させる照射法です。腫瘍の境界が明瞭で比較的限局しているなど、一定の条件を満たした腫瘍にのみ行える照射法です。通常、1日あるいは3〜5日間連日で照射が完了します。本治療オプションの適応性については、CT検査やMRI検査を元に、放射線治療医が決定します。
薬物療法(同義語:がん薬物療法、化学療法など)
細胞障害性抗がん剤
人間と動物の細胞障害性抗がん剤は基本的なコンセプトが異なるため、人間で一般的に言われている“体中の毛が抜ける”あるいは“吐き気が止まらない”等という強い副作用は比較的まれです。細胞障害性抗がん剤の投与は1−3週間に1回実施され、定期的な通院が必要です。細胞障害性抗がん剤によって、引き起こされる可能性がある副作用を下記に示します。
- 骨髄抑制(主に好中球や血小板の減少など)
- 骨髄抑制に伴う発熱(発熱性好中球減少症)
- 消化器障害(一過性の食欲不振、嘔吐、下痢、血便など)
- 血管外に薬剤が漏出した場合の周囲組織の壊死(ドキソルビシンやビンクリスチンなど)
- がん治療関連心血管毒性(ドキソルビシンなど)
- 出血性膀胱炎(犬のシクロホスファミド)
- アレルギー反応(L-アスパラギナーゼなど)
- 一過性の皮膚の色素沈着および・あるいは脱毛や被毛の質の変化
※その他、抗がん剤の種類によって上記以外の副作用が認められることがあります。
分子標的薬
腫瘍細胞の特定の分子を標的にした新しい治療法です。分子標的薬の副作用として、消化器障害、好中球減少症、肝酵素上昇、腎機能障害、皮膚障害(色素脱、皮膚炎)、その他高血圧などが認められることがあります。分子標的薬による治療中は、身体検査や血液検査などを定期的に実施する必要があります。
電気化学療法(ECT)
ECTは近年開発された新しい治療法で、全身麻酔下で実施されます。短時間の高電圧パルスと細胞障害性抗がん剤(ブレオマイシン±シスプラチン)を組み合わせる治療方法です。高電圧パルスが抗がん剤の細胞内への取り込みを増強させ、抗腫瘍効果が向上することが知られています。また、高電圧パルスを組み合わせることで、細胞障害性抗がん剤の投与量は少量でも十分な効果を発揮するため、全身投与時に一般的に認められる骨髄抑制や胃腸障害は、ほとんど認められないのが特徴です。副作用として、ECT実施部位の一過性の疼痛、びらん、発赤や腫脹などがあります。
免疫療法
人や動物自身のがんに対する免疫を高めてがんを攻撃する治療法です。現在、日本の医療においてがん患者に一般的に使用されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害抗体薬(抗PD-1/PD-L1抗体、抗CTLA-4抗体)とキメラ抗原受容体(CAR)-T細胞療法の2つであり、いずれも進行したがん患者においても著しい治療効果を発揮しています。
一方で、獣医療において、国内で承認されている免疫療法は、犬口腔内メラノーマに対するDNAワクチンOncept®(Boehringer Ingelheim社)のみです。そこで、当センターでは進行期のがんの動物に対しても有効な治療法を提供するために独自に開発した犬と猫の免疫チェックポイント阻害抗体動物薬(抗PD-1抗体)を用いて、さまざまな腫瘍に対する獣医師主導臨床試験を実施しております。本試験にご興味がありましたら、当センターまでお問い合わせください。
緩和ケア
緩和ケアとは悪性腫瘍と共存しながら腫瘍による痛みや苦しみを軽減させ、自宅で快適な日々を過ごせることを目的した治療法です。緩和ケア単独で用いられる場合にもありますが、近年では積極的治療を行う場合でも同時に実施することが推奨されています。下記に代表的な緩和治療をご紹介致します。
疼痛緩和(痛みの治療)
緩和放射線治療
疼痛や機能障害などの不具合が、動物の生活の質に悪影響を与えている場合、もしくは近い将来、それらが発生する可能性が高い場合に実施されます。通常1〜3カ月程度、徴候を軽減することが可能で、根治的放射線治療で見られる様な副作用が発生しにくいことが特徴です。通常は、1週間に1回、全身麻酔下で合計3〜6回照射します。
緩和外科治療
腫瘤の一部を切除し、機能障害、疼痛、出血などを一過性に軽減する治療法です。原則的に延命には繋がりませんし、切除後の再発を免れることはできません。
非ステロイド系抗炎症剤
非ステロイド系抗炎症剤(犬:フィロコキシブ、猫:メロキシカムなど)は、癌性疼痛の治療薬としてまず始めに使用されます。ロキソニン®やアスピリン®の仲間の薬剤です。鎮痛作用だけでなく、一部の悪性腫瘍では抗腫瘍作用も認められると報告されています。まれに消化器障害(食欲不振、嘔吐、血便など)および/あるいは腎機能障害が発生することがあります。そのため、服用する際には定期的な身体検査や血液検査が推奨されます。
フェンタニールパッチ
注射薬や内服薬で痛みをコントロールできなくなったとき、医療用モルヒネの一種を使って疼痛を抑える治療法です。フェンタニールパッチは頸部背側に貼布する貼り薬で、週に1〜2回、麻薬取り扱い免許を有する動物病院で貼り替える必要があります。フェンタニルパッチの鎮痛作用は強く、副作用は比較的軽度です。
各種鎮痛薬
トラマドール、ブプレノルフィン、ガバペンチン、プレガバリン、フネルベトマブ、ベジンベトマブなどが上記の痛みの治療と併せて用いられることがあります。
栄養治療について
がん性悪液質とは、がんを伴う動物に認められる合併症のひとつです。通常の栄養サポートでは完全に回復することができず、体重減少、筋肉量の持続的減少、食欲不振などを伴います。がん性液質が進行すると、生活の質の低下が低下するだけでなく、治療の予後にも影響を与えます。この病態から離脱するためには、適切ながん治療はもちろん、全栄養素がバランスよく配分された食事を確実に摂らなければなりません。そのために、各種栄養チューブ(胃ろう、チューブ、食道ろうチューブ、経鼻チューブなど)が用いられることがあります。これらのチューブを用いると、動物に過度のストレスを与えることなく、理想的な食事の摂取や日々の投薬が可能となります。
サリドマイド
腫瘍の増殖に必要不可欠な血管新生を妨げる薬剤で、同時に抗悪液質作用(栄養状態の改善)も有します。主な副作用に嗜眠(眠くなること)が挙げられます。