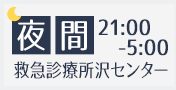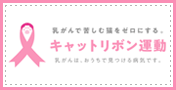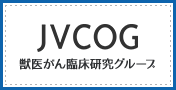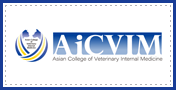見学・研修に関するガイドライン
ホーム > 人材育成 > 見学・研修に関するガイドライン > 全科研修医について
全科研修医について
1.応募資格
日本国獣医師免許取得者。新卒・既卒のいずれも可とする。
2.研修開始時期
4月、10月の年2回
3.募集・選考について
| 募集人数 | 2名 |
|---|---|
| 選考方法 |
|
| 選考期日 | 研修開始3カ月前までには当センターに問い合わせ、および審査書類の送付を完了すること |
4.研修期間
原則2年間。
5.諸待遇
有給制(月額20万円、時間外手当は別途支給)、1日8時間勤務・原則週休2日間、その他、基本的な就労条件は常勤に準ずる。
6.研修科目
腫瘍科、小動物消化器センター(胃腸、肝胆、膵)、総合診療科(皮膚科、循環器科、眼科を含む)、外科/麻酔科、画像診断科、臨床検査科(細胞診)、救急診療科
7.研修目標
(1)一般目標
- 獣医学教育課程において修得した獣医学に関する知識・技能を臨床実務に応用できるものとして体系化する。
- 科学的思考力、応用力、判断力を身につける。
- 暖かい人間性と広い社会性を身につける。
- 臨床経験を通じ、総合的視野、想像力を身につけ、獣医師としての社会的責務を果たす能力の向上を図る。
- 飼育動物の飼養者の獣医療に対する要望並びに飼育動物に関する保健衛生及び公衆衛生指導の対応を学ぶ。
- 獣医療における経済性を学ぶ。
(2)専門科目標
- 一次診療で治療困難な疾患や稀少疾患に対し、専門医が提供する知識や技能を集中的に学ぶ
- CTやMRIの画像診断の適応疾患や読影技術を学ぶ
- 応用外科手術の周術期管理に携わることで、適応症例の決定ができるようになり、ご家族様へのインフォームドコンセントができるようになること
- 各科専門医のもとで症例を多角的に診断・治療するチーム医療に対応できる力をつける
- カルテ文書や画像データを適切に管理・保存できることとすること。
- データ集積方法および研究報告までのながれを修得すること
- 国内外の論文報告を正しく解釈し、自らの診療に取り入れること
- 化学療法剤の取り扱いおよび調剤方法を修得すること
- 症例検討会(CPC)において獣医療情報を収集し、総合的に疾患を分析・判断できること
8.研修内容
- 研修の年間スケジュール:1カ月を1単位とし、以下の単位数にて年間12単位取得するものとする。
2年目も同様のスケジュールとする
- 腫瘍科:2
- 小動物消化器センター(胃腸、肝胆、膵):2
- 外科/麻酔科:2
- 夜間救急診療:2
- 画像診断科:1.5
- 臨床検査科(細胞診)x0.5
- 総合診療科(皮膚科/眼科/循環器科)×2
- 学会参加:2年目に研究会あるいは学会での発表を1演題選択可能
- CPC(月1回第3木曜日20時〜22時30分)の出席
9.指導体制
以下の指導獣医師のもとで研修を実施。
- 腫瘍科:小林哲也
- 小動物消化器センター(胃腸、肝胆、膵):中島亘
- 外科:廉澤剛、藤田淳
- 夜間救急:
- 総合診療科:
・皮膚科:村山信雄
・眼科:小野啓
・循環器科:岩永孝治 - 画像診断科:小野晋、戸島篤史
- 麻酔科:長濱正太郎
10.研修医の評価
(1)評価時期
各科の研修期間終了後に指導獣医師が評価を行い、研修継続可否について、6カ月に1回、研修委員会で評価を行う。
(2)評価項目
- 正しく問診が取れているか
- 次の基本的検査法について適応を決定するとともに必要に応し゛て自ら検査を実施し、結果を解釈て゛きているか
・血液検査(血液一般検査、血液生化学的検査等)
・画像検査(超音波検査、エックス線検査等)
・その他の検査(尿検査、ふん便検査、細菌検査等) - 適切な鑑別診断をあげることができ、イニシャルプランニングができているか
- 必要な獣医療情報の収集、症例の検討により、総合的に問題を分析・判断し、評価か゛て゛きているか
- 飼育動物の飼養者との良好な人間関係のもとて゛問題に対処て゛きているか。
- 診療簿、検案簿等の文書を適切に作成し、管理て゛きているか。
- 他の獣医師やスタッフ等の獣医療関係者と協調・協力し、的確に情報を交換し問題に対処て゛きているか。
(3)研修委員会について
- 研修委員会の構成
委員会責任者:廉澤剛
委員会構員:
小林哲也
中島亘
白石陽造 - 研修委員会の開催回数 :2回/年
- 役割と権限
委員会を開催し、指導獣医師の評価に基づく終了審査を行う。
研修終了時に修了証の交付を実施する。