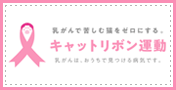中森あづさ(日本小動物医療センター カウンセリング部部長)
はじめに
「この子は自分の娘より可愛いんです」と言い切る飼い主を目の当たりにして、「ああ、こういうことまで口にできる時代になったんだな」と思うと同時にちょっとたじろいだのは3年前のこと。
獣医師の1人として、飼い主の1人として、またジャーナリズムに関わる者として長きにわたり小動物獣医療を眺めてきたが、ここ十数年のペットを取り巻く環境の変化、小動物獣医療の多様化はめまぐるしく、こうした変化に臨床獣医師はどれだけ対応し得るのだろうか、ということを常々感じていた。そうした大きなうねりのなかで根底に流れる飼い主の気持ちをいかに受け止めるか、という課題について、心理カウンセラーのボランティアおよび勉強を続けていたところ、2004年1月より、ある動物病院にて週1回飼い主のケアを行う機会を得ることができた。その後丸3年を経て、獣医師と飼い主がより良いコミュニケーションをとることこそが、今後の小動物獣医療の基本となり得るという思いを強くしている。
そこで、これから数回にわたって、わかっているようで実はわかっていない「コミュニケーション」たるもの、また今後求められる小動物獣医療の方向性といったものについて綴ってみたい。
飼い主の多様化に応えるために
それこそ、ひと昔前に出会ったある飼い主は、自分の犬が健康なうちに動物病院に連れて行き、糞便検査だけをしてもらうと語っていた。「健康な時から良い動物病院をみつけておけば、安心だもの」。糞便検査でその動物病院の雰囲気、獣医師やスタッフの態度などを見極め、そして、A動物病院はワクチンやフィラリア予防用、B動物病院はちょっとした怪我や慢性疾病用、C動物病院は重篤な病気用などと使い分けるという。その当時は「熱心な飼い主もいるもんだなー」と思っていたが、今やそうした飼い主は珍しくない時代となった。
もちろんそれに呼応するように、動物病院もさまざまな形態で展開されるようになってきたことはご存知のとおりである。それこそ一次診療vs二次診療、ホームドクターvs専門医といったくくりだけでは分類できない、飼い主の求めるさまざまな要望に焦点を当ててサービス部門を特化させたような動物病院も展開されている。
「ペットは家族の一員」という認識が市民権を得てから、飼い主の求めるものは増え続ける一方である。これらに応えていくためには、まず飼い主が何を欲しているかを知らなければならない。そのために必要なものは、飼い主といかにコミュニケーションをとっていくかということになる。
「コミュニケーション」という言葉に、飼い主にへりくだる、またはかしずくというイメージを持つ獣医師がいると聞いたこともあるが、コミュニケーションとは「意思のやりとり」であって、そこに上下関係は発生しない。日本の文化のなかには「あうんの呼吸」とか「以心伝心」などと言われるように、言葉にしなくとも自分の思いは相手に伝わるものだという思い込みがあるが、現在これだけ多様な文化が入り混じる日本において、また世代間格差も広がりつつあるなか、言葉にしなくて通じるものがどれだけあるのだろうか。
コミュニケーション・エラーを認識しているか?
今まで1週間に1回は耳掃除に来ていたミニチュア・ダックスフンドのルークちゃんが、ここ1カ月以上来院していないことに気づいたとする。その時あなたはどう思うか?
「飼い主さんが忙しいのかな?」「耳の調子がよいのかな?」確かにそうかもしれない。しかし、実はちょっとしたコミュニケーション不足により転院している可能性も高いのである。コロラド州立大学獣医学部Argus Institute に勤務するカウンセラー、Barabara L Beach氏は「獣医師に対する不満の90%はコミュニケーション・エラーによるものである」と言い切っている。さまざまな人種が入り乱れる米国ではコミュニケーションが重要視されているが、この話をそうした米国だからこそと捉えるか、米国でもそうなのかと思うべきか…。
インフォームド・コンセントという言葉、概念を知らない獣医師はいない時代になったとは思うが、今、小動物獣医療で扱われているのは、インフォームドの部分であり、コンセント(自己決定)の部分にまで至っていないと思うのは私1人ではないだろう。飼い主にどのような情報を伝えていくか、だけではなく、その情報をどのように伝えていくか、といった部分についても知ることが、インフォームド・コンセントには大切になる。
「いまさらコミュニケーションなんて」と思われる諸氏も多いだろうが、コミュニケーション法を学んで損はない。これからますます多様化する飼い主を受け入れていくためにも、その重要性を認識してもらえればうれしいと思う。
次回からは具体的なお話にします。
今回のまとめ
より良いコミュニケーション法は勝手に身につくものではない、学ぶものである。